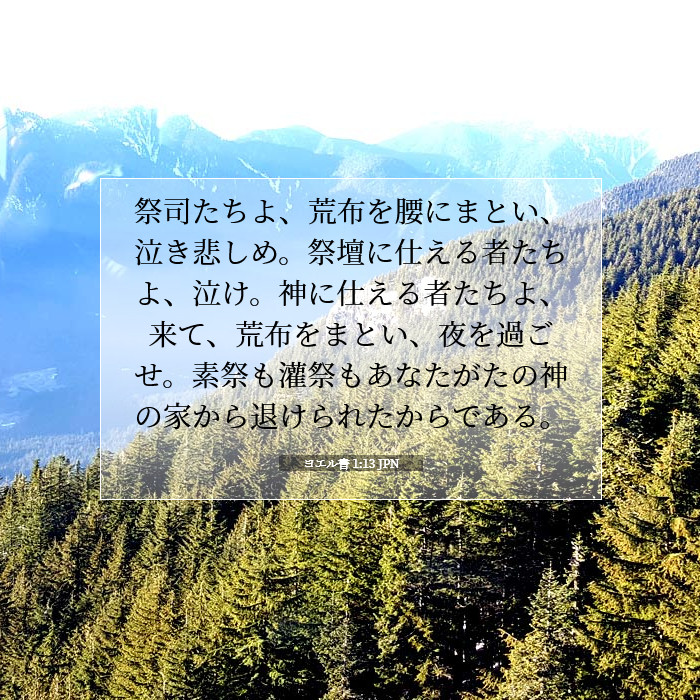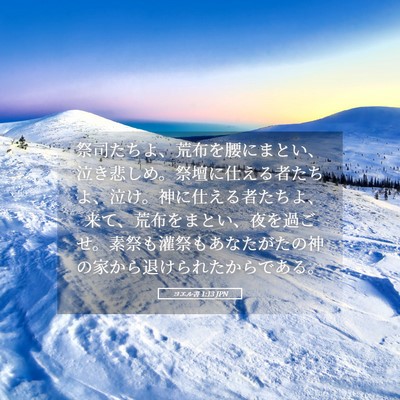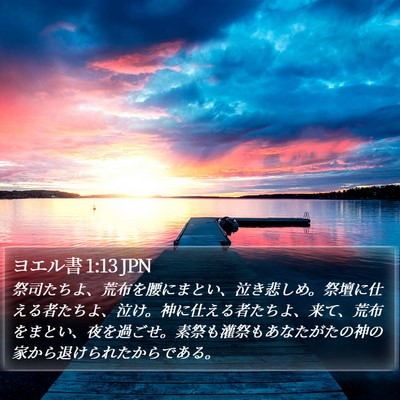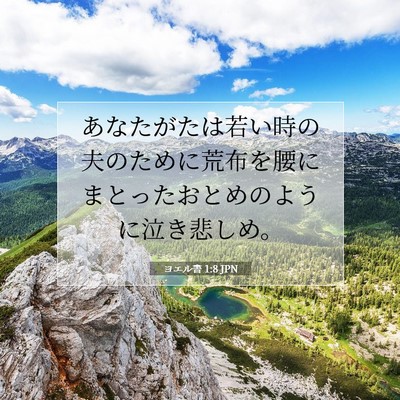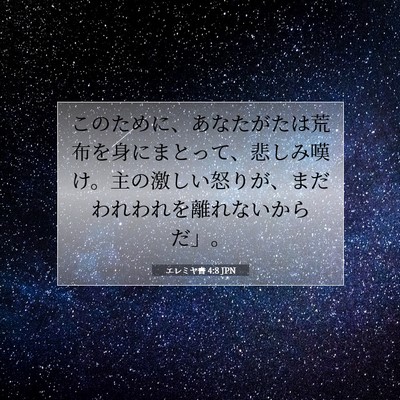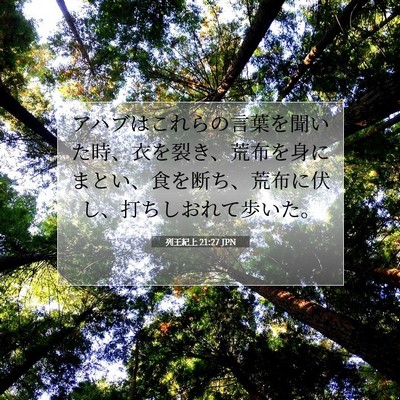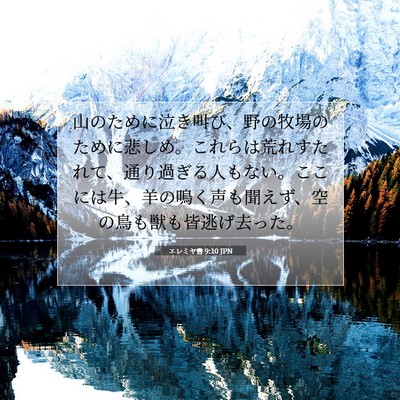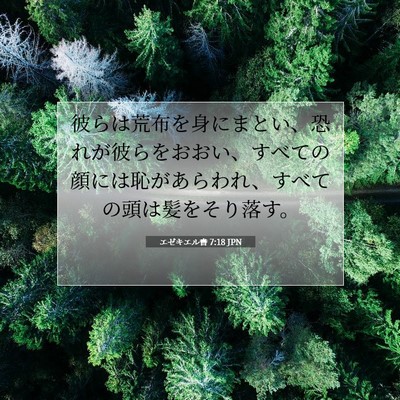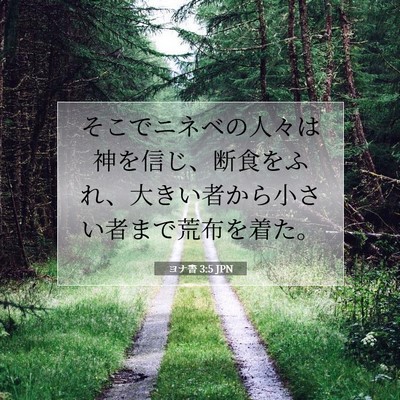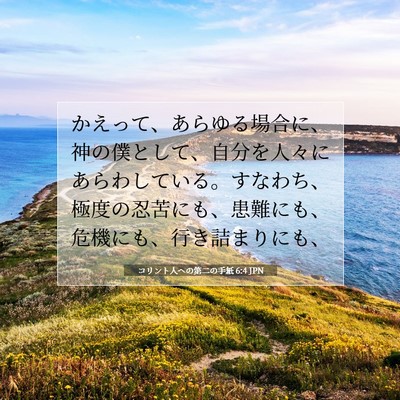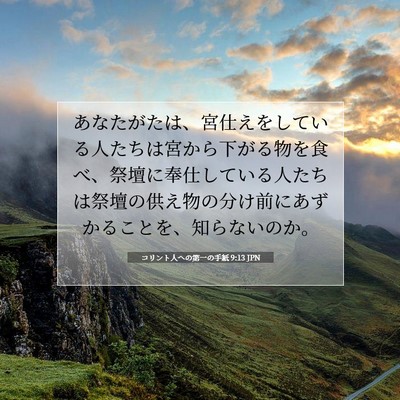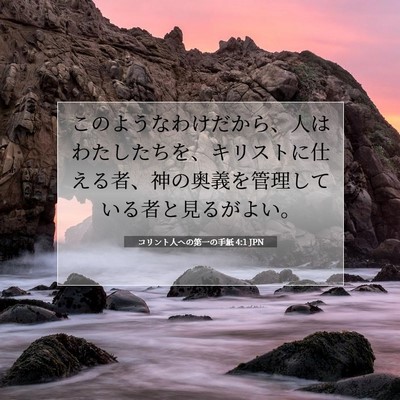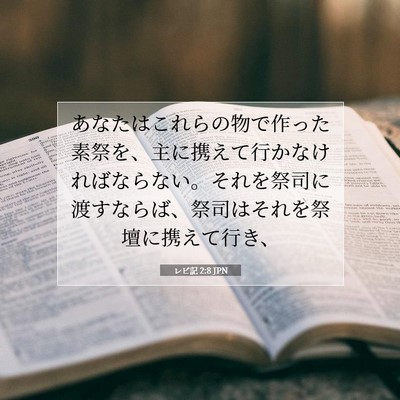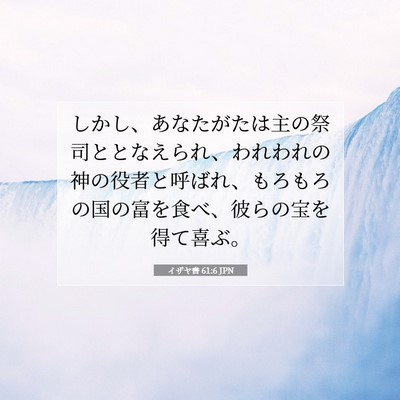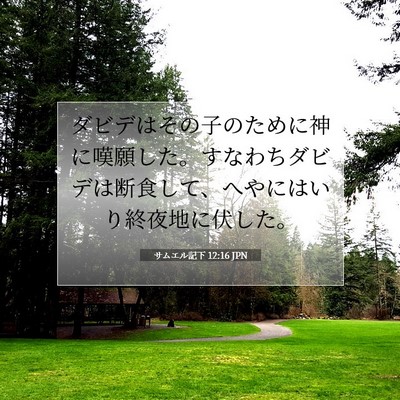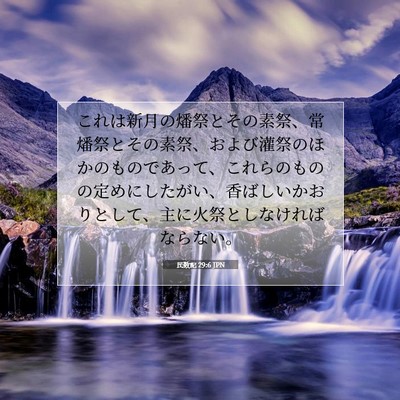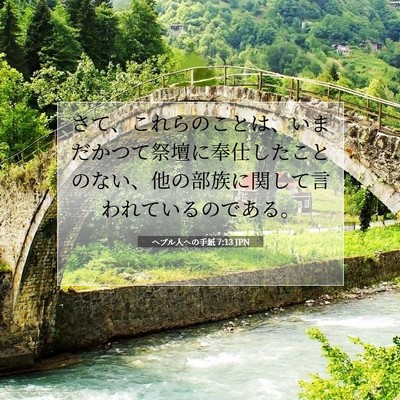ヨエル書 1:13 聖書の一節
ヨエル書 1:13 聖書の一節の意味
祭司たちよ、荒布を腰にまとい、泣き悲しめ。祭壇に仕える者たちよ、泣け。神に仕える者たちよ、来て、荒布をまとい、夜を過ごせ。素祭も灌祭もあなたがたの神の家から退けられたからである。
ヨエル書 1:13 交差参照
このセクションでは、聖書の理解を深めるために設計された詳細な交差参照を紹介します。以下には、この聖書の一節に関連するテーマや教えを反映した厳選された聖句が表示されます。画像をクリックすると、関連する聖書の一節の詳細な分析と神学的な洞察が表示されます。
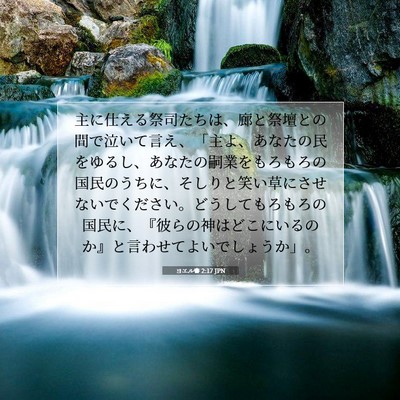
ヨエル書 2:17 (JPN) »
主に仕える祭司たちは、廊と祭壇との間で泣いて言え、「主よ、あなたの民をゆるし、あなたの嗣業をもろもろの国民のうちに、そしりと笑い草にさせないでください。どうしてもろもろの国民に、『彼らの神はどこにいるのか』と言わせてよいでしょうか」。
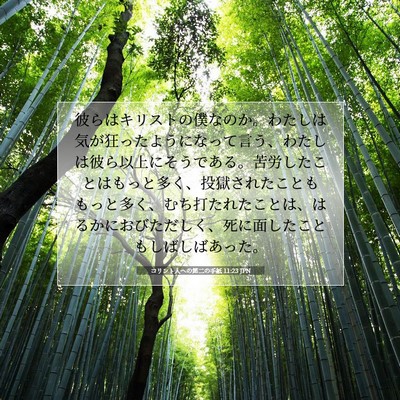
コリント人への第二の手紙 11:23 (JPN) »
彼らはキリストの僕なのか。わたしは気が狂ったようになって言う、わたしは彼ら以上にそうである。苦労したことはもっと多く、投獄されたことももっと多く、むち打たれたことは、はるかにおびただしく、死に面したこともしばしばあった。
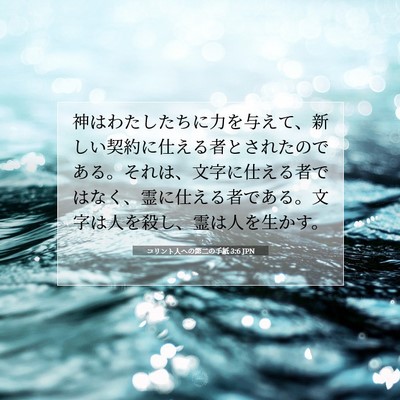
コリント人への第二の手紙 3:6 (JPN) »
神はわたしたちに力を与えて、新しい契約に仕える者とされたのである。それは、文字に仕える者ではなく、霊に仕える者である。文字は人を殺し、霊は人を生かす。
ヨエル書 1:13 聖書の一節の注解
ヨエル書 1:13 の聖句解説
ヨエル書 1章13節は、神の民に対する警告と悲しみを表しています。この節では祭司たちに対し、哀悼の態度を求められています。その解釈と意味を探るために、著名な公的ドメインの解説者たちの見解を結び付けます。以下に示すのは、マシュー・ヘンリー、アルバート・バーンズ、アダム・クラークの見解からの要約です。
聖句の内容
「祭司たちよ、腰を巻いて哀れみの声を上げ、祭壇の前に立ちなさい。」(ヨエル1:13)この節は、祭司たちに対して悲しみと悔い改めの態度を求め、国の問題を神に持ちかけるように求めています。
聖句の意味と解釈
-
悔い改めの呼びかけ:
ヨエルは、神の民に対して悔い改めを促しています。神の怒りが襲っている時、祭司は特にその役割を果たさなければならず、神に赦しと助けを求めることが必要です。 (マシュー・ヘンリーによると、祭司は神と民との間の仲介者であり、彼らの罪を取り去る役目がある。)
-
神の非の察知:
この節は、自身の罪を認識し、神の非の中での悲しみを強調しています。禍が降りかかった時、いかに神に近づくかが重要です。 (アルバート・バーンズは、この悲しみが神への正しい反応であると説明している。)
-
祭司の責任:
祭司たちは民の霊的指導者として、神の言葉を適切に伝えなければなりません。彼らの役割は神と民との間に横たわる義務であり、それを果たさなければならない。 (アダム・クラークは、祭司がこの役割を持つことにより、彼らの責任がより重要であると強調している。)
関連する聖句の交差参照
- イザヤ書 58:5 - 断食の本当の目的について。
- ヨエル書 2:12-13 - 悔い改めて神に返ること。
- エズラ記 9:5-6 - 民の罪を神に告白する。
- 詩篇 51:17 - 神が求める心の悔い改め。
- マタイによる福音書 5:4 - 悲しむ者たちの幸い。
- ルカによる福音書 18:13 - 自己認識を持った罪人の祈り。
- 使徒言行録 2:38 - 悔い改めの重要性と聖霊の受け取り。
聖句のテーマ的な考察
ヨエル書 1:13は、悔い改め、悲しみ、神との関係性を強調する重要な節です。聖書全体を通してこれらのテーマは繰り返し登場し、他の数多くの節に関連しています。この節を理解することで、聖書の他の部分との関係性を把握することができます。
聖典を横断する解釈の方法
聖書全体を通じてテーマを見つけ、文脈に沿った解釈を行うことは、神の言葉を深く理解する鍵となります。特に、悔い改めというテーマは旧約聖書と新約聖書の両方で一貫しており、信者が求められる姿勢を示しています。
結論
ヨエル書 1:13は、私たちに神に近づく重要さを教えてくれます。祭司たちだけでなく、すべての信者がこの警告を受け止め、悔い改めて神に寄り添うべきです。この聖句を通じて、私たちの信仰を深め、他の聖句とのつながりを見出すことができます。神の言葉を理解するための手段として、聖書の交差参照を利用することで、より豊かな信仰の旅が待っています。
※ 聖書の一節の注解はパブリックドメインの情報に基づいています。内容はAI技術によって生成および翻訳されています。修正や更新が必要な場合はお知らせください。ご意見は、情報の正確性と改善に役立ちます。