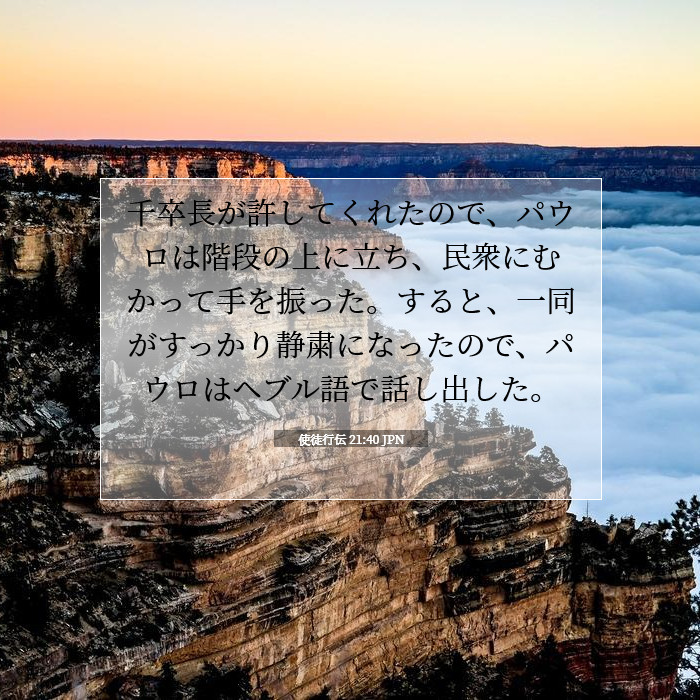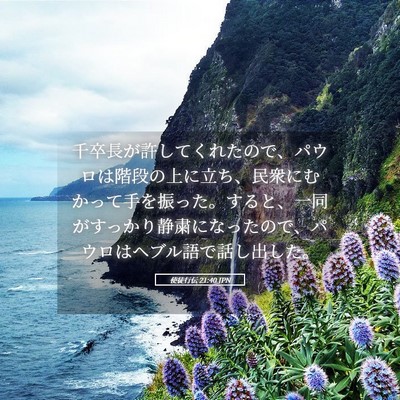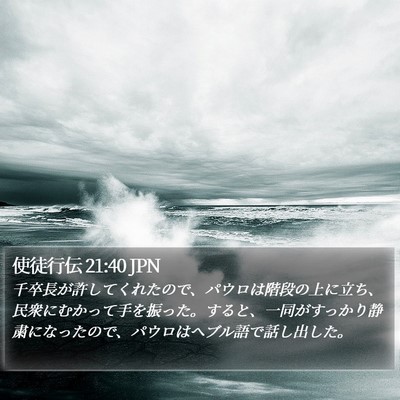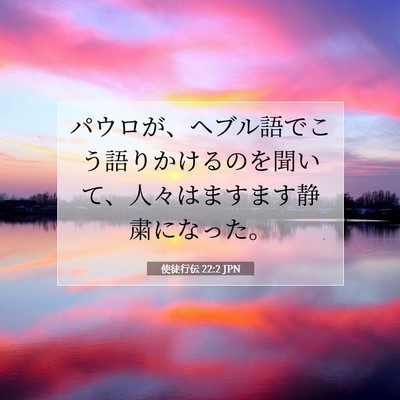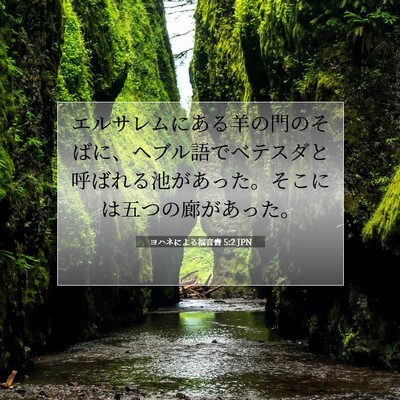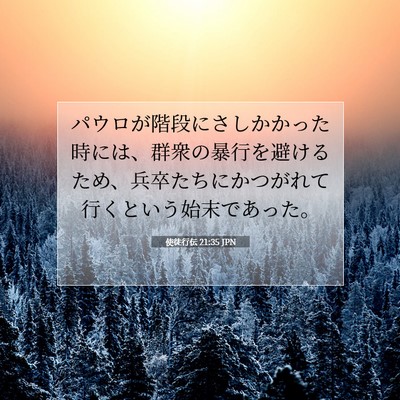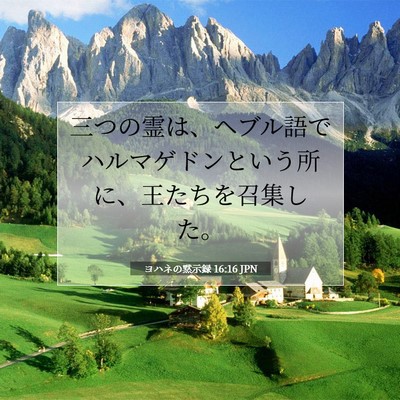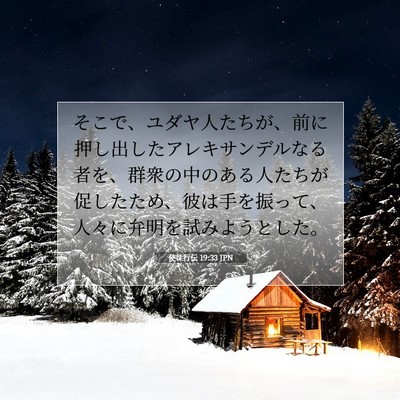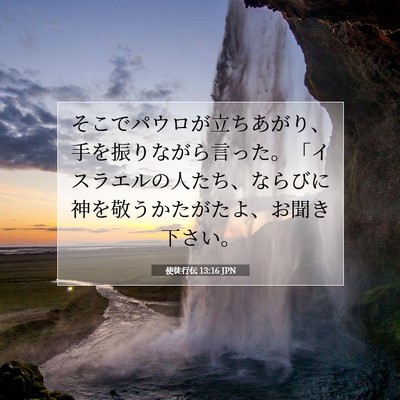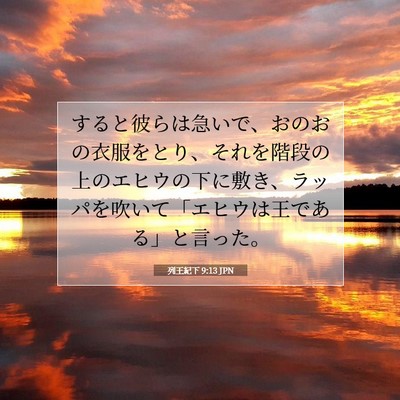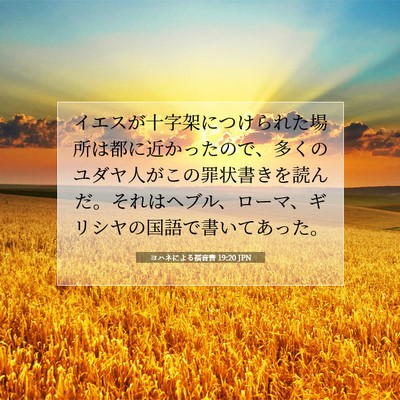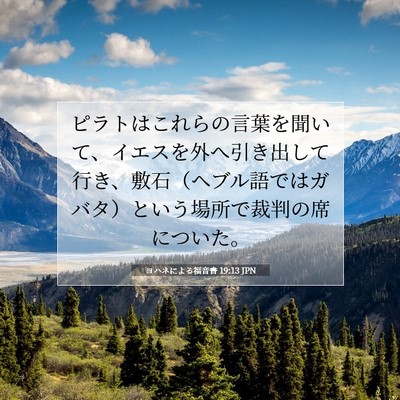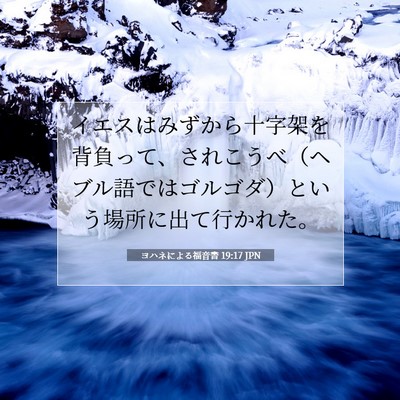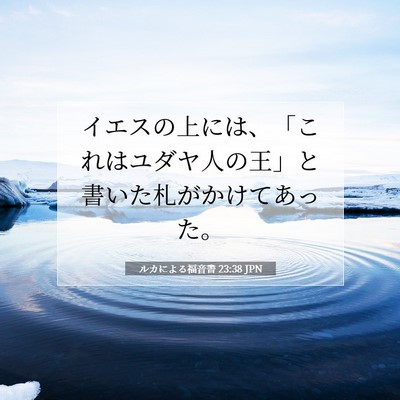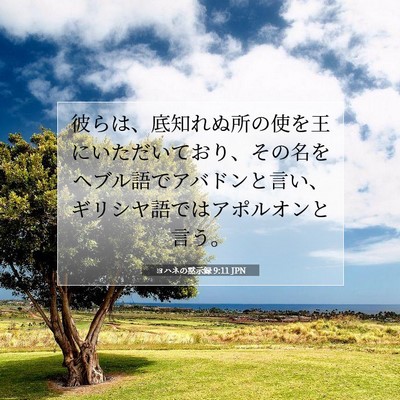Verse
使徒行伝 21:1 使徒行伝 21:2 使徒行伝 21:3 使徒行伝 21:4 使徒行伝 21:5 使徒行伝 21:6 使徒行伝 21:7 使徒行伝 21:8 使徒行伝 21:9 使徒行伝 21:10 使徒行伝 21:11 使徒行伝 21:12 使徒行伝 21:13 使徒行伝 21:14 使徒行伝 21:15 使徒行伝 21:16 使徒行伝 21:17 使徒行伝 21:18 使徒行伝 21:19 使徒行伝 21:20 使徒行伝 21:21 使徒行伝 21:22 使徒行伝 21:23 使徒行伝 21:24 使徒行伝 21:25 使徒行伝 21:26 使徒行伝 21:27 使徒行伝 21:28 使徒行伝 21:29 使徒行伝 21:30 使徒行伝 21:31 使徒行伝 21:32 使徒行伝 21:33 使徒行伝 21:34 使徒行伝 21:35 使徒行伝 21:36 使徒行伝 21:37 使徒行伝 21:38 使徒行伝 21:39 使徒行伝 21:40使徒行伝 21:40 聖書の一節
使徒行伝 21:40 聖書の一節の意味
千卒長が許してくれたので、パウロは階段の上に立ち、民衆にむかって手を振った。すると、一同がすっかり静粛になったので、パウロはヘブル語で話し出した。
使徒行伝 21:40 交差参照
このセクションでは、聖書の理解を深めるために設計された詳細な交差参照を紹介します。以下には、この聖書の一節に関連するテーマや教えを反映した厳選された聖句が表示されます。画像をクリックすると、関連する聖書の一節の詳細な分析と神学的な洞察が表示されます。
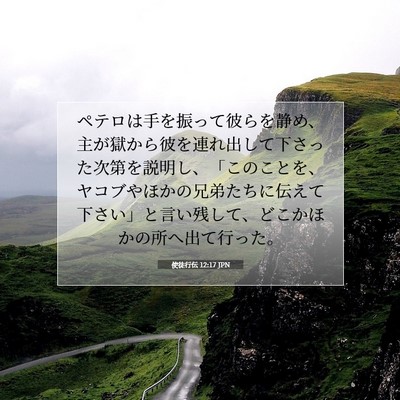
使徒行伝 12:17 (JPN) »
ペテロは手を振って彼らを静め、主が獄から彼を連れ出して下さった次第を説明し、「このことを、ヤコブやほかの兄弟たちに伝えて下さい」と言い残して、どこかほかの所へ出て行った。
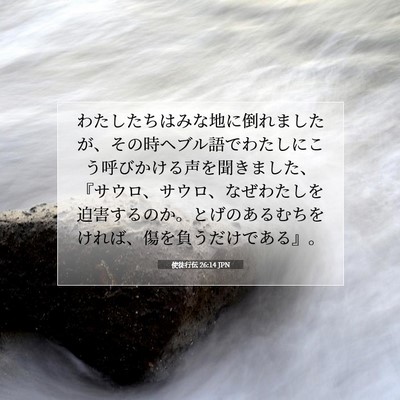
使徒行伝 26:14 (JPN) »
わたしたちはみな地に倒れましたが、その時ヘブル語でわたしにこう呼びかける声を聞きました、『サウロ、サウロ、なぜわたしを迫害するのか。とげのあるむちをければ、傷を負うだけである』。
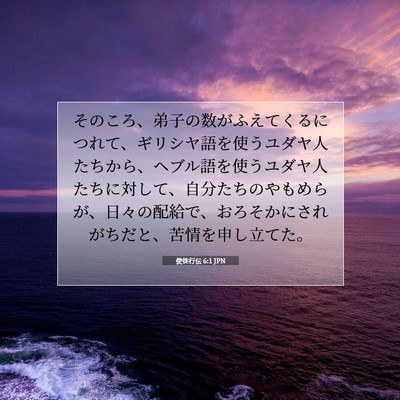
使徒行伝 6:1 (JPN) »
そのころ、弟子の数がふえてくるにつれて、ギリシヤ語を使うユダヤ人たちから、ヘブル語を使うユダヤ人たちに対して、自分たちのやもめらが、日々の配給で、おろそかにされがちだと、苦情を申し立てた。
使徒行伝 21:40 聖書の一節の注解
使徒行伝 21章40節 の解説
聖句:「そこで、パウロは手をあげて民に合図した。静まった後、彼はヘブライ語で彼らに語りかけた。」
この聖句は使徒行伝の中で非常に重要な場面を描写しています。パウロが民衆に対して語りかける準備をしているところです。この状況は、彼の使命が異邦人のためだけでなく、イスラエルの民に対しても向けられていることを示唆しています。
この聖句の解釈
以下に、注解者たちの見解をまとめました:
-
マシュー・ヘンリー:
彼は、パウロが群衆に手を上げて合図をしたことが、彼が自身の背景を考慮に入れて行動していることを示していると説明しています。パウロは、元々ユダヤ人であり、彼らに親しみを持って接することで、メッセージを受け入れやすくしようとしています。
-
アルバート・バーンズ:
彼は、パウロが「ヘブライ語で語る」ことを強調し、彼がイスラエルの民とのつながりを重視していることを指摘しています。この言語の選択は、彼の忠誠心を示すだけでなく、聴衆に対する彼の配慮を鮮明にします。
-
アダム・クラーク:
クラークは、パウロが静まらせるための手を上げた行為を、彼が要求するメッセージの重要性を強調していると述べています。この行動は、彼が信仰の表明としての説明を試みる際の彼の巧妙さを示しています。
聖句の背景
この時期、パウロはエルサレムにおり、彼の活動に対する抵抗や誤解が多く存在しました。彼は、ユダヤ教の法律に従って生きている自らの背景を利用して、民衆とのコミュニケーションを図ろうとしています。
関連する聖句
この聖句に関連する聖句を以下に挙げます:
- 使徒行伝 22章1節 - パウロの弁明。
- 使徒行伝 9章15節 - 主がパウロを選んだ理由。
- 使徒行伝 26章4-5節 - ユダヤ教における自身の背景についての説明。
- 使徒行伝 15章13-21節 - 神が異邦人に福音をもたらす計画。
- フィリピ 3章5-6節 - パウロのユダヤ人としての経歴。
- ローマ 1章16節 - 福音はすべての人に力を与える。
- ガラテヤ 1章11-12節 - パウロの使徒職の権威。
聖句のテーマと意義
この聖句は、パウロの使徒としての使命の重要性を浮き彫りにします。彼は、自らのアイデンティティを考慮し、聴衆にアクセスするための手段を太くすることで、福音を効果的に広めようとしています。
結論
使徒行伝 21章40節は、パウロが群衆に語りかけるための準備をする重要な瞬間を示しています。この聖句は、神の計画に従って行動することの重要性を教えており、パウロの信仰の道を辿る上での教訓となります。
※ 聖書の一節の注解はパブリックドメインの情報に基づいています。内容はAI技術によって生成および翻訳されています。修正や更新が必要な場合はお知らせください。ご意見は、情報の正確性と改善に役立ちます。
使徒行伝 21 (JPN) Verse Selection
使徒行伝 21:1
使徒行伝 21:2
使徒行伝 21:3
使徒行伝 21:4
使徒行伝 21:5
使徒行伝 21:6
使徒行伝 21:7
使徒行伝 21:8
使徒行伝 21:9
使徒行伝 21:10
使徒行伝 21:11
使徒行伝 21:12
使徒行伝 21:13
使徒行伝 21:14
使徒行伝 21:15
使徒行伝 21:16
使徒行伝 21:17
使徒行伝 21:18
使徒行伝 21:19
使徒行伝 21:20
使徒行伝 21:21
使徒行伝 21:22
使徒行伝 21:23
使徒行伝 21:24
使徒行伝 21:25
使徒行伝 21:26
使徒行伝 21:27
使徒行伝 21:28
使徒行伝 21:29
使徒行伝 21:30
使徒行伝 21:31
使徒行伝 21:32
使徒行伝 21:33
使徒行伝 21:34
使徒行伝 21:35
使徒行伝 21:36
使徒行伝 21:37
使徒行伝 21:38
使徒行伝 21:39
使徒行伝 21:40